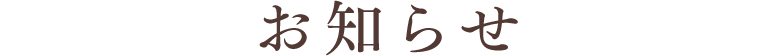2025/08/27その他
おかげさま農場と歩んだ10年~もち米「マンゲツモチ」
8月初旬、田んぼは青々と稲が順調に育ち、出穂(しゅっすい)を迎えます。出穂とは稲の茎の中にある花や実がつく部分が成長して、茎の先から外に出て見えるようになることを指します。茎からはポツポツと白い花が付きます。花といってもパッと咲く花ではなく、数ミリの白い糸のような細い花でひっそりと咲く小さなものです。今年は酷暑の影響からか花の咲き始めが早く、やや黄色っぽい花でした。
 ▲稲の茎周りに付いている白いものが花です。出穂がはじまるとお米が実り始める合図です。
▲稲の茎周りに付いている白いものが花です。出穂がはじまるとお米が実り始める合図です。
さて、千葉県成田市の「おかげさま農場」と共にもち米「マンゲツモチ」を育て始めてから今年で10年経ちました。当社の大福や御赤飯を支えるもち米は、コシの強さと歯切れの良さが特長です。2015年から始まった共同取り組みは、今や当社の和菓子作りにとって欠かせない絆となりました。
出会いの始まりは2014年初夏。新店舗開発に伴い、既存商品の原材料を見直す中で、大福のもち米も改めて検討することになりました。いくつものもち米を試食した結果、最も理想に近かったのが「マンゲツモチ」。江戸っ子たちが粋と愛して好んだ“ブチっと切れる歯切れ”は、江戸から続く榮太樓の大福には欠かせない特徴です。その個性が見事に調和したことが決め手になりました。当社と関りのあった奥村氏の紹介で生産者の高柳功さんを紹介していただき、翌年から共同作業が始まりました。当時、高柳さんから出された条件は二つ。
「農家の大変さを理解し、一緒に取り組むことができるか」
「田んぼを拡げることになるから、中途半端でやめないこと」
こうして、社員、取引先である高島屋様、三幸食品様が田植えから除草、収獲まで体験する取り組みが始まりました。
5月・・・田んぼに入り、手作業での田植え
6月・・・隔週で雑草を抜く除草作業
10月・・・釜を持っての稲刈りと収穫祭
はじめは自分たちが食べる分(約0.2ha)の量しか作っていなかったが、今では約3ha(30枚分)の田んぼをすべて当社のために「マンゲツモチ」を作って頂いています。
代表の高柳さんと山倉亮太さんにこの10年を振り返り伺いました。
 ▲左が当場の代表高柳功さん、右が山倉亮太さん
▲左が当場の代表高柳功さん、右が山倉亮太さん
「もう10年、早いですね。はじめて会ったときの印象を思い出します。僕は会社務めの経験がないから企業ってよくわからないけど、想像していた堅い会社イメージと違って、榮太樓さんはどこか“会社っぽくない”というのかな、親しみやすくて自由な雰囲気があった。だからこそ一緒に続けてこられたんだと思いますよ。」と山倉さん。
苗づくりでは「水分・養分をギリギリにし、頑丈に育てる事」が何よりも大切だと高柳さん。今年は梅雨らしい雨もなく、猛暑続き。田んぼの水温を下げるために何度も水を入れ替える日も続きました。
農場名「おかげさま農場」の背景には代表高柳さんと、師と仰ぐ無着成恭(むちゃくせいきょう)先生との出会いがあります。無着先生の言葉「人は食べなければ生きられない」「食べれるということは幸せなこと」「自分だけで生きている人間はいない」といった“食は命”の教えを多くの人々に伝えてきました。高柳さんはその言葉に深く感銘を受け、昭和63年(1988)に当場を設立。「おかげさま」という言葉は「お陰様」と書きます。日々の暮らしも、自然の恵みも、自分一人の力ではなく、見えない誰かの支えによって成り立っている。その“陰”に感謝する気持ちを込め農場名を無着先生に相談したところ、「どうぞ使いなさい」と快諾をいただき農場にこの名前を授けました。「おかげさま農場」という名前には、人と人、自然と命をつなぐ感謝の心が込められています。
 ▲おかげさま農場の名前のルーツなどを話す高柳さん。
▲おかげさま農場の名前のルーツなどを話す高柳さん。
 ▲当場で穫れた西瓜を頂きました。とても甘かったです。右側は当場内に咲くひまわり畑
▲当場で穫れた西瓜を頂きました。とても甘かったです。右側は当場内に咲くひまわり畑
これから収獲までに注意するのはカメムシとスズメ。実を守るため、暑さに中での対策が続きます。お彼岸明けまでの辛抱を経て、10月初旬の収穫祭までもう少し。この秋もまた、感謝と喜びを分かち合える季節がやってきます。
おかげさま農場との10年は、単なる原材料の取引ではなく「つくる人」と「つかう人」が共に汗を流し、学び、感謝を深めた10年でした。これからも自然に感謝し、この田んぼから生まれるもち米と共に皆さまに美味しい和菓子を届けて参ります。
広報部